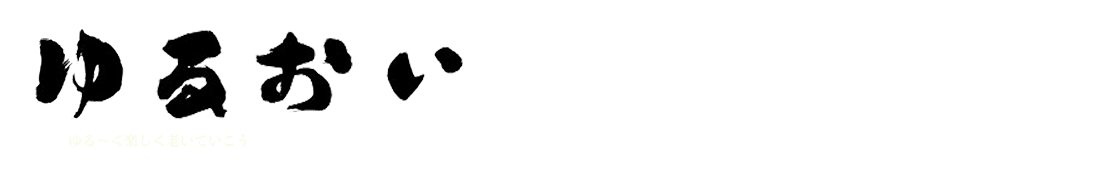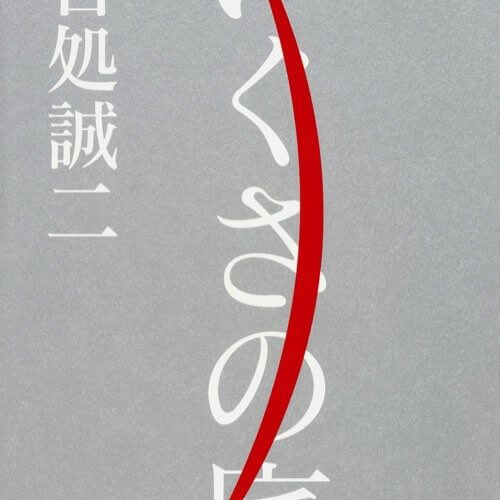フレンドリー・ファイアという言葉がある。味方の流れ弾に当たって死ぬことを言うらしい。どこで読んだかは忘れたが、戦時中の犯罪で二番目に多いのが「上官殺し」という話も聞く。戦時中、さも流れ弾に当たって死んだかのように見せかけて部下に殺されるのだ。
酷い話では、上官が、自分が味方の兵に殺されるのが嫌で自分の部隊の兵たちに銃を渡さなかったケースもあるという。自分本位の究極とでも言おうか。
戦争というのは、ある意味究極の人間劇の世界だ。
人は生きるために真剣にもなるし愚鈍にもなる。
隣人の死に敏感にもなることもあれば、鈍感にもなることもある。
己の精神を保つため、あらゆる手段を模索し、最適な方法を本能的に選択する。時には自己保身であったり、時には自己犠牲であったり。
そこには語られない、数えきれないさまざまな物語が存在するのだろう。
本作品、『いくさの底』は、2018年版このミス5位。作者の古処(こどころ)氏は2000年に『UNKNOWN』でメフィスト賞をとってデビューしている。
この人の作品を私は今まで読んだことがなかったが、著作は「戦争ミステリ」と冠がつけられるほど、「戦争・紛争」という特殊な舞台に拘っているという。
おそらくそういった戦時中の、見えない物語の魅力に魅かれてそのような舞台を選んでいるのだと思う。
「そうです、賀川少尉を殺したのは私です。」
物語は犯人の告白から始まる。
時代は第二次世界大戦中。敵である中国軍の侵攻を阻止するため、賀川少尉が率いる部隊はビルマの山岳地帯のとある村に駐屯することになった。
語り手は、部隊に同行した日本人通訳者。「軍人」ではない一般人の目を通して、日本軍の体質、特殊な環境におかれた村の独特な緊迫感や微妙な雰囲気が丁寧に描写されていく。
賀川少尉は過去にこの村に駐屯した経験があり、村人とは顔見知りで好印象を持たれていたらしく、村人も日本軍を歓迎。
・・・していたかのように見えた。
その賀川少尉が首を切られて殺される。夜中のトイレで。切断面から、凶器は村人たちが使っている特殊な鉈だと断定される。
見張りもいるし、凶器も特殊。となれば、賀川少尉を殺すことのできる者は限られている。犯人はすぐに見つかるのではないか。
だが味方の日本軍にも、村人にも、敵である中国軍にも、殺害の機会はあり、可能性は払拭できない。そもそも少尉の死をおおっぴらにするわけにはいかないので大掛かりな捜査もできない。
コトを荒立てないために、村人たちには「少尉は急な病気で本隊に運ばれた、容体は安定しているから安心するように」と伝えられ、少尉のいないまま、中国軍の侵入を警戒した裏山の探索は続けられる。
そんな中、今度は、この村の村長が殺される。少尉と同じように鉈で首を切られて。
村長を殺したのは本当に敵である中国兵なのか? 日本軍ではないのか? 次の殺人は発生しないと言い切れるのか。次に殺されるとしたら、それは誰だ? 村人か、日本兵か。村人と軍は、次第に疑心暗鬼になっていく。。。
まあ、ミステリーだし「実は敵に殺されてましたー」はないよなあ。じゃあ犯人は村人か味方の日本兵かどっちかか。殺し方的にはトリックモノじゃないから怨恨だよな。
村人の犯行だったとしたらなんだかんだで全員共謀とか。日本兵だったら実は動機は戦争とは全然関係ないところの私怨でした、って感じかなー。
などと素人考えで浅はかな先読みをしつつ読んでいたらばいかんせん。
ちゃんとこの設定ならではの結末が用意されておりました。なるほどこうきますか。
本作はあくまでフィクションだが、戦時中は似たような事件がザラにあったのではないかと思わせる、ミステリーにとどまらない臨場感あふれる作品だ。
「名探偵、皆を集めてさてといい」といった展開ではなく、謎解きが爽快なワケでもなく、全体の印象としては重苦しい感じが最初から最後まで続くため、人にとってはこの世界観に入り込めないかもしれない。
だが一度読み始めると、暗いなー、地味だなー、と思いつつもいつの間にか引き込まれ、気がつけば最後まで読んでしまい、読後にタイトルの意味含めていろいろと考えさせられている自分に気づくだろう。そんな一冊。